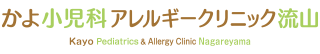2023年9月22日
登園の目安
第50号:2023年09月号
発熱を含め他症状があって受診した際に、「いつから登園できますか?」と聞かれことがよくあります。この答えは「今は何とも言えません」です。われわれは、お子さんを診察して必要に応じて検査をし、今日の診たてやこの後数日で予測される経過をご説明しています。月齢にもよりますが、特に乳児や幼児期早期のお子さんの病状は刻々と変化するので、そのまま良くなることもあれば急激に悪化することもあります。少なくとも受診後2-3日はご自宅で療養し、登園の目安について悩ましければ受診していただくことが望ましいと思います。
ただ、保育園児の親御さんは働いています。3日も休めないという状況もあるでしょう。私は9園の園医をしています。年2回健診に伺うのですが、今年の5-6月はどの園もここは病児保育室?と疑うほど、ぜいぜいしているお子さんがたくさんいらっしゃいました。特に0歳、1歳児クラスでその傾向が強く、園の保育士さんや看護師さん(常駐している園もある)から「熱が下がると、すぐに預けていかれます。」という嘆きをお聞きしました。園に預ける目安=熱がないことでは残念ながらありません。この点は、われわれ小児に関わる医療従事者や保育関係者と親御さんにやや解離があると感じています。特に0歳1歳は苦しい症状を自ら伝えられないため、診察することでわれわれがそれを代弁しているつもりです。時には、「こんなに苦しい咳をしている間は、たとえ熱が下がっていても、もう少し自宅で療養しましょう。」とアドバイスすると仕事は責任があるため、みなさん残念そうなお顔をなさいます。
いつになったら?何歳になったら?この状況から脱せられるのかと思い悩むこともあると思いすが、2歳半~3歳くらいから驚くほど熱も出さなくなり、感染して症状がでることも少なくなります。それでも感染症には流行期があり、登園していると残念ながら度々もらってしまいます。働く親御さんの置かれている状況は(私も経験しているので)十分理解できますが、われわれはあくまでもお子さんファーストで療養していただけるように、引き続き診断してご説明していくつもりです。
どんなに責任のある立場でも仕事の変わりはいます。でもお子さんの親の変
わりはいません。たとえ疎まれながらも、「登園は無理しないように・・・。」と今日もこれからも言い続けます。