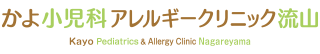院長コラム
のぞみ133号
2024年6月8日
のぞみ133号
第59号:2024年6月号
ゴールデンウィークに東海道新幹線に乗っていると、静岡県で緊急停止しました。その時左窓から大塚製薬の大きな工場が見えたので、後で調べてみると静岡県袋井市という場所でした。新幹線内のアナウンスでは、「車内の緊急停止ボタンが押されましたので、緊急停止しました。」その5分後くらいに、「13号車でお子さんが転倒して怪我をしています。この中に、医師や看護師の方がいらっしゃいましたら、至急13号車までお越しください。」
8号車の通路側に座っていた私は、猛ダッシュで13号車に向かいました。すでに看護師の方が一人いらっしゃいましたが、一番後ろの座席と壁の隙間に横向きでベビーカーが置かれていて、そこに座ってユーチューブを見ていた3歳くらいの女の子が、ベビーカーごと後ろに倒れて、後頭部が3㎝くらいぱっくりと割けて出血していました。
すぐにベビーカーを引っ張り出してデッキまで移動しました。新幹線スタッフの方から手袋を借りて傷口を診ようとしていたら、ちょうど外科の先生もいらして、「このくらいの傷なら、救急外来でもよく診るレベルだから、目的地の駅で降りたら病院に受診して、ホッチキス(のような医療器具)で留めてもらえばいい。」と親御さんに説明していたので、すかさず「小児科医です。先生すぐにナート(傷口を針と糸で縫う)しなくてもいいのですね?緊急性はないですね?」外科の先生は、「大丈夫です。水道水で洗えばいいです。」
私は新幹線スタッフに「緊急性はないので、今すぐ新幹線を走らせてください。」と伝え、新幹線が走り出した後に、ナースさん、他のドクターと共に、ベビーカーの上に座る女の子の頭の傷をペットボトルの水で洗浄し、しばらく圧迫してしっかり止血していることを確認してから、ガーゼを4つ折りにして傷口に当てると、ナースさんはお子さんの髪の毛を、左右上下こよりのように巻いて十字に結び、ガーゼで保護してくれました。さらにテープでとめたところで、一連の処置を見ていた外科のドクターが慣れた手つきで包帯を巻いてくれ、さすがにネット包帯は新幹線にはなかったので、巻いた包帯を固定する目的で子ども用の帽子を被せて処置は終了しました。
所要時間は、わずか7-8分程度だったと思います。たまたまその新幹線に居合わせた医療従事者達が、阿吽の呼吸で団結して処置にあたったことに、とても誇らしい気持ちになりました。その後、「今救護にあたって下さった方々は、お名前と住所をお願いします。」とスタッフに声をかけられましたが、誰一人その場に残らず、何事もなかったかのように各々の席へと戻っていきました。
新幹線は20分程遅れましたが、大幅な影響はなかった模様ですし、お子さんも無事に目的地まで行けたかな、でも座席じゃないところに座るのはさすがに危険だから、親御さんは今後きちんと座席に座らせて欲しいな(きっと懲りたでしょう)とその日の夜はふと考えながら眠りにつきました。
改めて、医療従事者のパワーってすごいなと感慨深い旅でした。
迷惑行為の背景にあるもの
2024年5月2日
迷惑行為の背景にあるもの
第58号:2024年5月号
医師約70人がGoogleの口コミに関して提訴しました。インタビューを受けた医師は、必要のない薬だから処方しなかったが、処方してもらえなかったと一方的に口コミに書かれた。スタッフの悪口を書かれた、病院が閉院したと嘘の情報を流された等多岐にわたっています。
もちろん当院も例外ではありません。最近でも、息が苦しいのでマスクを着用せずに来院したいという電話の申し出に対して、院内の感染対策(症状がなくても、お互いに潜伏期間で感染させてしまう可能性があるため)なので着用をお願いすると、感染を100%防げるというエビデンスを示してほしい、文章で出してほしいとのことでした。午前診療でものすごく忙しい時間帯に電話をかけてこられたので、その対応のためにスタッフの本来やるべき仕事が奪われました。
また午後は一般診療をやっていないので、症状ある時は午前受診をとみなさんにお願いしているにも関わらず、症状がでてきたから午後の予約時に定期薬処方と一緒に診て欲しいとの依頼がありお断りすると、きれて文句を言って電話をガチャンときられました。他にも、ネット予約をとらずに発熱外来に電話をかけてきたので、ネット予約をしていないので〇〇番目の診療になりますと説明すると、そんなことはホームページに書かれていない、なぜネット予約をとらないことをそんなに責められるのか、この件は口コミに書きますからねと言って電話をきられました。2年半ほど前には、私個人や家族に対しての直接的な脅迫もありました。完全に一方的な逆恨みでした。(あまりに酷い内容なのでここには記載できませんが)
ここに書いたことはほんの一部に過ぎません。無断キャンセルや予約時間に連絡なしで遅れてくる、親が欲しい薬を一方的に要求してくる、説明に納得しないで居座り、その後きれてお金を払わずに帰るなど、迷惑行為が後を絶ちません。そのため、院内に迷惑行為に関する張り紙をし、流山警察署にも相談して連携をとってもらうことになりました。われわれ医療者も生身の人間ですから、正直そういう迷惑行為には傷つきますし心が荒みます。
都がカスハラ条例を作ったように、飲食店やホテル、公的な機関(区役所や市役所)、保育園や学校でも常日頃から起こっているのです。では、どうしてこういう迷惑行為が後をたたないのでしょうか。それは人間的な未熟さに起因していると思っています。自分の思い通りにならない時に感情的にきれる、きれていいと思っている。怒りを相手にぶつけることで従わせようとする。怒る原因を作った相手が悪いと一方的に思わせて、自分に有利にことをすすめようとする。そういう心理が働いているのではないでしょうか。
「金持ち喧嘩せず」という言葉の意味は、お金を稼ぐようになる人は、理性的な人が多く(なかにはそうではない人もいますが)、感情的にならずに冷静に判断して、ことの解決にあたるということだと私は解釈しています。また物事の本質を見抜く力を持ち、礼儀や礼節を重んじることができるからトラブルにならないのではないでしょうか。
年齢は数に過ぎず、歳を重ねたからといって大人になれる(人間的に成熟できる)わけではありません。また、偏差値や学歴、社会的地位もあまり関係ありません。いくつになっても学び成長できるからです。多くの失敗や挫折を経験して、しっかりと自分の頭で考え、時には人の力も借りて乗り越えてきてこそ、人とし成熟していけるのではないでしょうか。
親が感情的にきれる行為を繰り返し見てきた子どもは、自分の思い通りにならなければ感情的にきれていいのだと認識していくことでしょう。それが正当な行為だと疑わなくなるでしょう。当院に迷惑行為をする方々もまた、その親からそのように育てられてきたのではないかと推察しています。子どもは思いのほか、親に直接言われたことよりも、親の生活習慣そして家族や他人に対する態度をよく観察しているものです。
子どもの成長=親の成長でもあります。われわれ大人も、子どもたちとともに多くの学びの中で人間的に成長していきたいと改めて思うこの頃です。迷惑行為やそれをする人たちとは今後も引き続き決別し、お互いに敬意を持って信頼関係を築いていける方々の幸せに、ほんの少しばかりでもお役にたてれば幸いです。
真の優しさとは何か?
2024年4月9日
真の優しさとは何か?
第57号:2024年4月号
新年度が始まりました。そして新たな環境で生活をスタートさせた皆さんは、さぞ期待と不安が入り混じっていることでしょう。お友達や先生との新たな出会いに、ワクワクするそんな季節がやってきました。一方で、しばらくするとお友達関係の悩みもでてくるかもしれません。小学校高学年や中学生のお子さん達から、診療の際にお友達関係の悩みを相談されることがあります。
大抵は言われた言葉にショックを受けたり、仲が良かったはずなのに突然冷たくされたりというお悩みが多いのですが、みなさん幼い頃から「お友達には優しくしましょう」という抽象的なことを言われ続けてきていませんか。では、みなさんにとって優しさとはどういうことでしょうか?優しい人というのはどんな人でしょうか?
私にとっては、自分が本当に苦しい時や辛い時、悩んでいる時に心からの慰めや励ましの言葉をかけてくれる人、何も言わずに見守り応援してくれる人、共に闘ってくれる人、敢えて厳しく助言してくれる人、その時々の状況にもよりますが、後から振り返ってみて厳しさこそが心からの優しさだったりすることも多々ありました。逆に優しそうなふりをする人もいます。そこには「打算」や「自己防衛」といった損得が潜んでおり、優しそうにしておいて相手を自分にとって都合よく利用しようと企んでいる。そういう押し売り的な優しさは、すぐに見抜かれてしまいますが、世の中結構多いものです。損得勘定でしか、人と関われないという人もいます。
楽しさを共有することは簡単ですが、苦しさを共有したり共感したりすることはかなり難しいことだと思います。人生経験を積む中で人格が形成されていき、人の痛みがわかることもあれば、歳を重ねても人としての優しい心を持ち合わせていない人もいます。
時代により価値観は変わり、優しさの判断基準も人それぞれだと思います。新たな生活を迎えるこのタイミングで、改めて自分にとって真の優しさとは何か、今までの関わり合いの中で有難かったことは何かを考えてみてはいかがでしょうか。
好きなことをみつける
2024年3月5日
好きなことをみつける
第56号:2024年3月号
この春卒園や卒業を迎える皆様、おめでとうございます。親御さんも様々なエピソードが走馬灯のように駆け巡っているのではないでしょうか。開院した当初、まだ保育園児(年長)だった娘もこの春小学校を卒業します。あっという間の6年間でしたが、学校でも学校外でも様々な経験をし、素敵な人たちとの出会い、そして受験を通してたくましく成長してくれました。入学式に校門前で撮った写真を見返すと、その頃から身長も36㎝以上伸びました。性格も気質も私とは全く違う娘ですが、最近では年の離れた友達感覚で楽しい会話が成り立っています。そして私自身も、娘の成長を通して学ぶこと、また反省することも多かった小学校生活でした。
中学校に入学したら、自分自身が夢中になれるものを見つけて欲しいと願っています。勉強のみならず、部活でも、学校行事でも、学校外のものでも何でもいい。とにかく時間を忘れて没頭できるもの=好きなことです。テレビ朝日の「博士ちゃん」という番組に出演されるお子さんたちは、みんな好きなことを生き生きと語っています。エジプト考古学に魅せられた女の子、葛飾北斎を敬愛する男の子、野菜ソムリエ、城マニア、地図マニア他、興味のある分野をとことん掘り下げて日々その知識を更新しています。
インターネットが普及して、必要な情報はいつでも検索できるようになりました。さらには生成AIの誕生により、我々の生活は今後加速度的に便利にはなっていくでしょう。AIにとって代わられる仕事がでてくるという議論も盛んですが、それでも人としての尊厳は変わることなく、むしろ優しさ、思いやり、繋がり、気遣い、心配り、モラルや敬意といった人としての基本的に大切な部分の価値が、より一層増していく世の中になると私は思っています。
自分の好きを見つけて没頭すること、人との繋がりの中でお互いを尊重し、励まし合い支え合いながら成長できること、お子さん達にはそういう人間力を磨いて素敵な大人になってもらいたいと切に願っています。そして我々大人も、それをサポートできるように学び成長し、人間力を磨いていきたいものです。
皆様の新たな旅立ちを心よりお祝い申し上げます。
万能薬はない!
2024年2月10日
万能薬はない!
第55号:2024年2月号
親御さんにとって都合のいい薬(欲しい薬)を希望されても処方はしていません。薬をもらうこと自体が目的で受診されている方がいらっしゃいます。それならば、ドラッグストアでいいわけです。われわれは、問診をとり診察させていただいた後、今のお子さんの病状をご説明し、その症状を改善するのに繋がると判断すれば、必要最小限にして処方しています。理由として副作用のない薬はないこと、そして飲む必要がなければ自然に治るからです。外用薬も同じです。ヒルドイドは単純な保湿薬ではなく、列記とした皮膚の治療薬であり、「皮脂欠乏性湿疹」という病名をつけて本当に必要な方のみに処方しています。
ウイルスの種類やお子さんの体質の違いによって、治るまでの期間は様々です。咳や鼻汁といった風邪症候群でも、数日以内に改善することもあれば、RSウイルスやインフルエンザウイルスでは気道の炎症が強くなるため、咳が数週間続くことや、コロナウイルスでは数か月続くこともあります。本来人間には、自然治癒力が備わっています。病院を受診して薬を飲めば、魔法のように良くなると期待して、すぐによくならないともっと強い薬が欲しいと翌日に受診され、またいくつものクリニックを転々とされる方もいます。
感染して発症して数日後にピークを迎えて、その後徐々に改善していくものです。高熱が続いたり、呼吸状態が悪化したり、眠れない、食べられない、中耳炎や肺炎、ひどい脱水等が疑われる場合には、診察後に必要に応じて追加の薬を処方したり、場合によっては入院できる施設をご紹介しています。処方の必要がない旨をいくらご説明しても納得していただけず、ひたすらもっと強く効く薬をと希望してくる方は、そもそも医療者の診療を信用していない、もしくは病気は薬ですぐに良くなるはずだと誤解されているのではないでしょうか。
流山市の小児科医の会議で、ある先生は「子どもの病気の9割は自然に治る。」とおっしゃっていました。まさにその通りです。一部の特殊な病気を除いては、自然に治ります。私は診察前に、「診察させて下さい。」とお声掛けをしています。決して一方的に診ているとか治しているなんて思っていません。これまで積み上げてきた知識や技術や経験を元に、改善に向けてあくまでアドバイスをして、みなさんご自身の力でよくなっていくのを、ほんの少し後押ししているにすぎないのです。われわれのアドバイスを聞いて納得し、やってみるかどうかは、ご自身やご家族の問題です。やってみたけれど思うように改善されない場合は、その都度話し合い、再度診察させていただき、新たな一手をご提案してまた実行していただく。この繰り返しです。ただし重症な病気の場合は、先述の通りその場で速やかに対応する必要があります。
何度も病院に来たくないから、すぐになんとかして欲しいから、まだ起こってもいない不安を抱えて、治療が思い通りにならないと一方的に医療者や薬のせいにして「治らない」と文句を言われる方がいます。それでは到底信頼関係を築いていくことはできません。これは医療の世界に限ったことではないと思っています。自分達の問題に対して、自分達でできるケアが他にもっとないのか、しっかり考えたり話し合っているのでしょうか。
万能薬はありません。良くなる力を信じて、お互いに敬意を払い、医療者と信頼関係を築いていきませんか。
自立するということ
2024年1月9日
自立するということ
第54号:2024年1月号
子育ての最終ゴールは、お子さんが自立した大人になり社会にでていくということではないでしょうか。では自立するということはどういうことでしょうか。広辞苑で「自立」と引くと、「他の援助や支配を受けず、自分の力で判断したり身を立てたりすること。ひとりだち。」とあります。まずは経済的な自立、自分で自分を食べさせていけること、生活できることだと思います。次に、精神的な自立、自分の考えを持ち、学び、自分の言動と行動に責任を持ち、自分の機嫌を自分でとれることだと私は思います。
お子さんは当然経済的には自立していませんが、精神的にすごく自立しているお子さんもいます。また大人でも、経済的には自立していても精神的に自立していない人、経済的にも精神的にも自立していない人もいます。前者は支配的な人が多く、後者は依存的な人が多いと感じます。支配的な人は、相手が自分の思い通りに動かないと一方的に怒りをぶつけてきては、こちらがあたかも悪いような錯覚をおこさせます。依存的な人は、自分がこんなに傷ついた、傷つけられたと被害的となり相手を責めます。支配的な人は医療者に対して、「無責任だ!」という言葉をよく使い、依存的な人は「冷たい!」という言葉をよく使います。
つまり、支配や依存と無縁で自立している人のベースにあるのは、信頼や尊敬であり、自分がどう感じるか、どうしたいのか、そのために今何が必要かを冷静に考え行動できます。そして、必要に応じて専門家の支援を求めます。専門家の知識や技術、経験に敬意を払い、最終的には自身で考えやるべきことをしっかりやる。自身がやるべきことをやらない人ほど、相手に対する要求やお願いをしてくる傾向にあります。
私自身職業小児科医ですが、結婚した方がいいとか子供を持った方がいいといった考えは実はなく、人それぞれでいいむしろ男女問わず自立することが最も大切なことだと思っています。私の友人達はみな経済的にも精神的にも自立しているので、支配や依存とは無縁です。そして、私の知識や技術や経験をプライベートで搾取することも一切ありません。いつでも認め合い、お互いの幸せを願える関係です。さて、お子さんが自立した大人になるためのサポート、2024年早速何からはじめましょうか。
自分の人生は自分で切り開いていく
2023年12月8日
自分の人生は自分で切り開いていく
第53号:2023年12月号
小学校2年生のKちゃんは、夏休み明け後の給食の時間に突然泣き出してしまいました。夏休みに札幌の祖母と叔父・叔母の元へ一人で(ジュニアパイロットを利用して)遊びにいきました。叔父と叔母夫妻はとても仲が良く、まだ当時子どもがいなかったのでKちゃんのことをものすごく可愛がってくれました。一緒にテニスをして遊び、小樽にも連れて行ってくれて猫のガラス細工を買ってもらいました。楽しい時間が終わり、2学期が始まりました。Kちゃんの両親は共働きで常に忙しく、エンジニアの父親は出張にでかけると1-2週間帰ってきません。常勤で働いていた看護師の母親も、週1回は夜勤がありました。今でいうところのワンオペ育児でした。父の出張と母の夜勤が重なると、Kちゃんは小学校近くの知人のおばさん宅に預けられました。おばさんのお子さんたちはもう成人していて、すでに働いていました。泊まって翌朝小学校に登校しました。
忙しい両親は次第にすれ違い、いつしか家の中で会話がほぼなくなっていました。たまに家族で食卓を囲んでも団欒はなく、Kちゃんは父親に話しかけ、母親に話しかけ、なんとか会話を繋ごうといつも必死でした。Kちゃんは一人娘だったので、自分が頑張らないとこの家族は成り立たないと常に緊張状態で、お家が休まる場所ではなくなってしまいました。そのうちKちゃんに異変が訪れます。人が何を言っているのかが気になってしょうがなくなります。「3日前お父さん何話していたの?」 学校でも学童でも電車の中でも、気になって気になっていちいち確かめたくなりました。お友達が学童で先生に話しかけていると、そのお友達が去った後先生のところへ行って、「〇〇ちゃんは今何って言っていた?」学童の先生はその都度優しくKちゃんに話しかけてくれました。母親がつとめていた病院の小児科の先生にも話を聞いてもらいました。
3年生になり、同級生に髪の毛のない女の子Nちゃんがいました。その子の自宅はKちゃんの家と学校の間にあったので、Kちゃんは朝その子を誘って一緒に学校に行くようになりました。小児がんで抗がん剤治療をしていたから、髪の毛が抜けてしまったようです。担任のA先生は、ふさぎがちだったNちゃんを誘って学校に来てくれて嬉しいと、Kちゃんに表彰状をくれました。A先生は、子どもたちが素敵なことをすると、いつも表彰状をくれる優しい先生でした。
ある日Kちゃんがお友達の家に遊びに行くと、お友達のお母さんが塾で勉強すれば地元の中学ではない別の学校に行けることを教えてくれました。Kちゃんの地元の中学校は当時、校内暴力がひどくて校舎の窓がバリンバリンに割れていました。あそこの中学には行きたくないと思ったKちゃんは、帰ってから両親に頼んで、塾に行かせてもらうことにしました。塾では違う小学校に通うお友達もできて、切磋琢磨しながら3年間勉強して別の中学に無事合格しました。
中学では軟式テニス部に所属して、部活に没頭しました。区大会で優勝し、私立リーグ団体戦でも優勝して卒業するときに学校からスポーツ賞をもらいました。両親はというと相変わらず忙しく、家の中で会話はありませんでしたが、Kちゃんも忙しくしていたので段々気にならなくなりました。腰を痛めてしまい、高校では部活を続けられませんでした。高校を卒業し、大学に進学し、仕事を始め、紆余曲折あり、今Kちゃんは自分の生まれ育った街とは別の街で、自分の名前のついたクリニックで小児科医として働いています。両親はKちゃんが大学生の時に別居し、卒業後に離婚しましたが、晩年は母親の病気をきっかけにまた一緒に暮らしていました。その両親ももうこの世にはいません。
両親に、育った環境に、いろいろ苦悩したこともたくさんあったけれど、大人になったKちゃんが今思うことは、自分の人生は誰のものでもないから、自分で切り開いていくものだということ。
境界線を意識してみる
2023年12月8日
境界線を意識してみる
第52号:2023年11月号
職業柄、お子様の病気(病状)と日々向き合うのですが、病気だけではなくお子様自身や養育環境、とりまく状況などにも時には踏込むこともあります。治療が必要となっても、当然幼いお子さんにとってそれは親を始めとする養育者にケアしてもらう必要があります。風邪や胃腸炎等その時々で完結するものもあれば、私が専門とするアレルギーの病気(アトピー性皮膚炎や食物アレルギー、喘息等)は、長期的に継続してケアしていく必要があります。
喘鳴を繰り返して、喘息治療が必要な旨をご説明しても納得してもらえなかったり、喘息治療を開始してもいつのまにか中断されてしまったりすると、われわれ医療従事者もさすがに堪えます。それはなによりお子さんのためにならず、特に喘息は呼吸不全となれば命に関わるからです。これまでクリニックからも、何十台と救急車で搬送しています。時に看護師が救急車に同乗して病院に向かうこともありました。以前は私も真剣になりすぎて、親御さんを責めるような口調となってしまい、結果何十倍の怒りとなって帰ってきたことも一度や二度ではありません。怒りの基本は押し返す力なので、これ以上踏込んで欲しくないという表現だと今は理解しています。
そこで意識するようになったのが、境界線です。お子さんの病気や病状に誠意をもって向き合い、その時々で真剣に説明をするけれど、それを受け入れるかどうかは相手(親御さん)の自由であるということです。また、私の説明では納得できなくても、その後状況が変わることもあれば、別の先生で治療にうまくのることもあるだろうと考えるようになりました。そしてお子さんには本来、病気を良くしていこうとする力が備わっています。それは人生をよりよいものにしていこうとする力でもあります。
この境界線を意識することは、自分自身を意識することにも繋がります。相手の境界線を越えて踏込み過ぎないようにすることは、相手にも自分の境界線を越えて踏込まれないようにすることが大切だとわかるからです。親子・夫婦・親戚・友人・仕事関係これは全ての人間関係に言えることだと思います。
大切な人間関係こそ境界線を意識して、相手の人生は相手のもの、自分の人生は自分のものとお互いに尊重していきたいものです。
時薬(ときくすり)
2023年10月20日